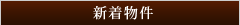
- 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,780万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,580万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,580万円 - 【長期優良住宅】上矢部4丁目新築戸建 1
矢部駅 4,480万円 - 東大沼2丁目新築戸建 1
古淵駅 4,180万円 - もっと見る
住宅エコポイント終了。住宅トップランナー基準はどうなる?
投稿日:2011年11月8日
■住宅版エコポイントが終了しました。
7月31日をもって着工したもので、エコポイントが終了しました。
それなれに効果はあったと思われます。お客様にすれば30万円がタダでもらえて、建物性能も省エネ性が高いのですから、一石二鳥といえますので、選択するのは当然といえます。
日本の住宅の省エネ性を高めなければならない政府としての、素晴らしいアイディアでした。
お客様・世論を味方につけて業界の改善を図っていくことができるのです。
そのためというか、その関連として「住宅のトップランナー基準」というものができて3年がたちました。
■住宅のトップランナー基準とは、省エネ法で定める「住宅事業建築主の判断の基準」のことです。
トップランナー基準の尺度となる省エネ基準は、断熱性を表す「熱損失係数(Q値)」と気密性を示す「相当すき間面積(C値)」によって判断されます。
Q値とは「:建物から逃げる熱量(W/K)/建物の延べ床面積(m2)」
C値とは「家全体の隙間の合計(cm2)/建物の延床面積(m2)」
また、住宅のトップランナー基準で重要視されるのは、窓や外壁の断熱性や気密性
①外壁や窓が「次世代省エネルギー基準(平成11年省エネルギー基準)」を満たす
②冷暖房設備や給湯設備のエネルギー消費量を、平成20年度時点での一般的な設備のエネルギー消費量に比べて、概ね10%削減する
上記の2つを満たすことが求められています。
そして省エネ基準を満たす外壁や窓を装備していること。その上で、
・高効率給湯設備や節湯器具
・熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
・太陽光発電設備
などを併設していることが条件となる。
また、省エネ基準を超える高い断熱性能を持つ外壁や窓(low-eなど)を備えた住宅は、それだけでトップランナー基準を満たす住宅と判断されます。
■住宅の省エネは推進されなければなりません。
脱原発の現在、co2削減公約目標を達成するためには、住宅の省エネを進めるしかありません。
それを推進してきた、住宅版エコポイントが終了し、9月末にはフラット35Sも優遇条件が少し下がります。それを補い、さらに省エネ率を高める手段はどうするのでしょうか?
国土交通省の腕の見せところです。
先日、国土交通省と業界団体(日住協)の意見交換会が開催できました。心配になって提案したら、業界団体の事務局が動いてくれて開催にこぎつけられました。
その中の話では、この辺のところは、国土交通省の担当者はよ~くわかっていました。
非常に苦しい台所事情で困っているところに、業界の各社の現状報告は予想外に良かったのです。担当者も一安心です。
私の予想より、戸建業界の省エネ対策は進んでいました。
ただ問題はあります。地方と零細です。
まず、販売価格が2000万以下の建物に省エネ装備のコストがかけられないということです。それと床暖房が計算上で不利になるので、それを補うコストをかける必要がでてきてしまいます。
それと、零細工務店において設計者の知識が少ない、薄い、古い場合に、対応策がわからないとか、面倒くさいなどで、導入に消極的ということがあります。
また、今年の省エネでいうと、暖房能力より冷房能力が問題です。さらには、電力不足による節電という事態も想定外です。多くの家で、エアコンをつけないさらには24時間換気を切るという事態が発生しています。
つまり、機械・設備による冷房から自然風による冷房にかわりつつあるのに対応できいません。
今年度は導入3年目で戸建分譲の50%目標というトッフランナー基準は達成すると思われます。
業界団体の意見交換会に参加の10社強だけでの話をまとめても、基準クリアーする戸数は2万5000戸超になります。首都圏全体で年間6万戸弱の着工ですから、その他の会社もやりますので、3万戸の目標はいくでしょう。
この調子ですから、2年後の100%に向かって、まだ時間はあるので、いろいろ考えたらいいでしょう。
そのうち、太陽光パネルが安くなり、一気に普及するかもしれません。
現在の太陽光パネルのコストが1/3になれば、ほとんどの戸建分譲に搭載されるでしょう。
- トラックバックURL
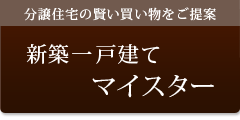
 地域から探す
地域から探す